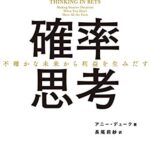悔しがる力 弟子・藤井総太の思考法(著者:杉本昌隆)の書評です。
【書評】悔しがる力 弟子・藤井総太の思考法 杉本昌隆
本書は、投資をするにあたって、非常に参考になる部分がありますので、トレーダーや投資家にとってもオススメです。
将棋は、ゲーム理論では二人零和有限確定完全情報ゲームに分類され、投資と違い、二人のゲームであったり、ランダムな要素がなかったり、全ての情報がプレイヤーに公開されているという点で投資とは異なりますが、ブル・ベアのように反対側の立場になって相手の手を考えたり、勝つために様々な戦法があったり、理詰めの思考法で最善手を積み重ねることによって勝ちにつなげるなど、投資と近い部分も多くあります。
二人零和有限確定完全情報ゲーム
- 二人:プレイヤーの数が二人
- 零和(「ゼロ和」と読むのが一般的だが「レイワ」とも読む):プレイヤー間の利害が完全に対立し、一方のプレイヤーが利得を得ると、それと同量の損害が他方のプレイヤーに降りかかる
- 有限:ゲームが必ず有限の手番で終了する
- 確定:サイコロのようなランダムな要素が存在しない
- 完全情報:全ての情報が両方のプレイヤーに公開されている
という特徴を満たすゲームのことである。
出典:wikipedia
その将棋のトッププレイヤーである藤井総太二冠、そして師匠の杉本昌隆八段(段位は2021年4月現在)の思考法を知ることは、トレードにもきっと活かせるはずです。
まず本書ですが、「弟子・藤井総太の思考法」というタイトルですが、師匠の杉本昌隆八段の話が多くの割合を占めます。
ですので、藤井総太二冠だけに興味がある方にとっては、少し物足りないと感じるかもしれません。
しかしながら、師匠である杉本昌隆八段もプロ棋士であり、日本将棋連盟の「よくある質問」によると将棋人口1200万人(レジャー白書2020によると620万人)のうちのトップ100(2021年現在の現役棋士が173名であり、杉本昌隆八段のレーティングは85位)には確実に入っている実力者であると考えられるので、そんな一つのゲームを極めた方の思考法も知ることができるのは、大変、貴重です。
勝負の世界で生き残るために、どのような思考法で、どのような取り組みをし、そして、どのような経験をしてきたのかといったことが書かれています。
まず印象に残ったことは、AIの使用についてです。
将棋界では、2017年に行われた人工知能(AI)であるポナンザと対戦した電王戦で、当時、名人であった佐藤天彦先生(現九段)に2連勝し、AIが人間に勝利しました。
そして、そこからもAIは年々強くなっており、もはや人間の力では追いつけないレベルになっています。
そんなAIを50代である杉本昌隆八段も研究で使用し、年配者の棋士にも使うべきと推奨しています。
それとは逆にAIでの研究ばかりしている若手棋士には、温故知新で古典的な勉強をしてみてはどうかと説きます。
これは投資の世界でも同じようなことが起きており、HFT(高頻度取引)などのアルゴリズム取引やAIが市場に投入されており、その使用法についても何が正解なのか誰もわからない状態になっています。
このまま全員がAIを使ったら、どのような値動きになるのか、投資の世界においてはAIが絶対になることはあるのかなど、わからないことだらけです。
ただ、一つの可能性として、AIによって合理的な行動を起こすトレーダーが増えれば増えるほど、逆に勝てなくなることが考えられます。
そんな時に、古典的な投資の格言が役立ったり、元の相場に戻ることが予想されます。
将棋においても、AIに頼らないオリジナル戦法を駆使する棋士が逆に勝っているケースもあります。
AIと自らの思考、そして古典的な知識の蓄積、将棋も投資も行き着くところは同じなのかもしれません。
藤井総太二冠の思考法で印象に残っているのは、「結果を求めない方が結果を出せる(引用:杉本昌隆『悔しがる力 弟子・藤井総太の思考法』株式会社PHP研究所, 2020年,p77」というところです。
これはトップアスリートやその他のトップ棋士に共通する思考法で、トップに立つ方は考え方が同じだと思いました。
投資においては、どうしてもお金を失いたくない、取り戻したいと結果である残っているお金について考えてしまいがちですが、焦点はお金ではなく、どのように期待値の高い上手いトレードができるのか、負けても悔いがないトレードができるのか、そちらを考えた方が最終的には生き残れるということです。
将棋では勝ちたい気持ちが強すぎると、最善手ではない、例えば、受ける必要がないのに玉を固める手を指してしまい、それが結果的には相手の攻めを呼び込む形になり、負けになってしまうというようなことが起こります。
投資でもその一回を勝ちたいためにランダムで動いている相場に入り、ナンピンを繰り返し、数回は勝てても結局は大損してしまうのと同じです。
結果が最も大事だからこそ、自分の実力を高めることに集中する、そんな当然なことを意識させてくれます。
またタイトルにある「悔しがる」というのは、投資にはおいてはタブーであるような風潮があるように思います。
なぜなら、投資において感情的になってよいことは何もないからです。
ですが、悔しがるというのは、モチベーションになることから、必ずしも投資においても悪いことではないと、本書を読んで思いました。
もちろん、トレーディングの最中に悔しい思いを抱えたままエントリーするのはよくありません。
大事なのは、切り替えです。
本書でも、負けの後の切り替えの大切さが書かれています。
トレードでは負けると休息を取ることが大切だとされますが、まさにそれです。
休息をして、気持ちを切り替えることができれば、負けた後の悔しい気持ちというのは、むしろあった方がいいと思います。
これは何も裁量に限ったことではなく、システムトレードにおいても同じで、なぜそのシステムが負けたのか悔しい気持ちがないと、よりシステムを改良しようというモチベーションに繋がりません。
負けた時は素直に悔しがり、その気持ちを研究へのモチベーションとし、気持ちを切り替えてトレーディングに向かうというサイクルを一貫してできるかどうか、それが大切だと思いました。
トレードにおける非効率的な勉強法について考えてみる

本書には、杉本先生から見て藤井二冠がいかに非効率的な勉強をして、そして、それが成長につながっているのではないかといった話が出てきます。
ここで言う非効率的な勉強法とは、即効性はなく時間もかかるし、はた目から見ると苦しいけれど、着実に自分の力になるような勉強法を指します。
そのような頭に汗をかくような勉強法は、トレードでいったら何になるでしょうか?
一つは、自分が行ったトレードの見直しです。
どこで、なぜそこでエントリーしたのか、そして、どこで、なぜそこで決済したのか、一つ一つチャートをプリントアウトして、文字に起こしてみる方法です。
スキャルピングやデイトレードであれば、トレード回数も多く、そのような作業をするのは非常に骨の折れる作業です。
ですが、そのように自分のトレードを見直して反省し、次のトレードに活かせている人がどれくらいいるでしょうか?
その他に非効率的な勉強を考えてみると、自分がトレードする対象以外の検証です。
例えば、FXで主にユーロ/ドルでトレードしていると、どうしてもその通貨ペアだけの検証に終始してしまう傾向があります。
ですが、例えば原油であったり、金であったり、違う対象を検証すると、相関性であったり、新しい投資手法が見つかったり、色々な発見があるかもしれません。
また本間宗久や牛田権三郎といった昔の相場師の考え方を学ぶといったことは、例えば、将棋でいう天野宗歩や大橋宗英といった昔の棋士の棋譜を学ぶといった、AIが発達した現代では非効率と思える研究のように思えますが、意外と役立つかもしれません。
まずは古今東西に目をやり、あらゆる勉強法を考えること自体が非効率かもしれませんが、実はそれが成長につながる確実な方法かもしれません。